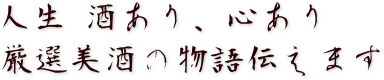先日吉祥のメンバーで宮崎の佐藤焼酎製造場さんへ訪問してきました。
先日吉祥のメンバーで宮崎の佐藤焼酎製造場さんへ訪問してきました。
大自然に囲まれた素晴らしい場所にその蔵はありました。祝子川(ほうりがわ)の脇にたたずむ建物は美術館のようです。焼酎製造だけでなく、人が集う場所としても活用されているそうです。


水江社長に案内していただきながら様々なお話をお伺いしました。温和で穏やかな語りの奥には、数々の苦難を乗り越え、厳しくも深い哲学がありました。
フラッグシップの「銀の水」の名前の由来もお聞きしました。蔵の後ろを流れる祝子川の水面が、太陽の光で銀色に輝いている光景の美しさから名づけたそうです。洗練された上品な味わいの麦焼酎にピッタリのネーミングですね。
また健康で、体に優しくお酒を楽しんで欲しい、「人に潤いを提供したい」という想いを持たれ、リニューアルされた天の刻印の裏ラベルには、水江社長の写真と共にその想いが記されています。ぜひチェックしてみて下さいね。またボトルも今まで見たことのないデザイン。何でも自動車の先端デザインから着想を得たそうです。
仕込み水にも恵まれており、70Mもボーリングしてやっと掘り出した地下水はいっさい濾過せずに使えるほど純度の高いもので、150年もの年月を経て上流域の地下水脈からゆっくりと下ってきたものだそうです。
そして焼酎廃液のリサイクルにも力を入れており、循環型のエコな焼酎造りを実践しています。
自然とロマン、そして情熱が融合した蔵元さんでした。皆さんもぜひ飲みながら想いを馳せてみて下さい。
去る8月2日、鹿児島県西酒蔵の真喜志 康晃さんをお招きしてイベントが開催されました。今回は2部構成で
第1部は新羽にある地鶏焼き 味くり家 にて、料飲店のお客様を対象に「料飲店情報交換会」が、
第2部は吉祥サロンにて、一般のお客様を対象に「宝山を楽しむ会」が開催されました
まずは第一部、味くり家にて、天使の誘惑ソーダ割りにて乾杯!

その後、真喜志さんより、焼酎の基礎知識や西酒蔵の焼酎に賭ける想いを語っていただきました。
「焼酎とは文化である」
この言葉が印象的でした。
前掛け姿がとももお似合いの真喜志さん、熱い方です!
日吉にある、「やまへい」さんとの一コマ


参加者の皆様お酒談義に花を咲かせています。
続いて第2部、吉祥サロンにて

一部と同様、天使の誘惑で乾杯!




最後に吉祥スタッフと記念写真!今日のこの日のために、日曜日の休日にもかかわらず、丸一日吉祥のためにお時間を割いていただきました、西酒蔵 真喜志 康晃さん、本当に有難うございました。
これからも吉祥は焼酎の文化を伝えていきます。
現在34歳の蔵元、小宮山善友さんが造り5年前に発売された非常に個性豊かな麦焼酎です。
常圧蒸留により、重厚で深みのある味わいを生み出し、旨味でもあり雑味でもあるフーゼル油(蒸留後、貯蔵時に浮いてくる脂分)を網ですくい取り、その加減により味の個性が決まるそうです。
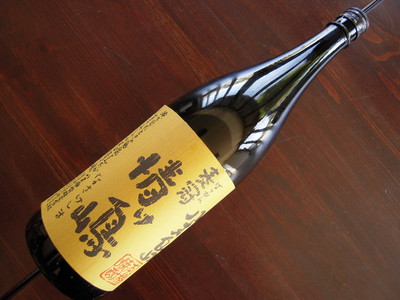
発売当初、「こんな癖のある焼酎売れないよ」と周囲の声は冷ややかなものだったそうですが、小宮山さんが求めていたのはスッキリして飲み易い焼酎ではなく、「おじいさんの時代に飲まれていた骨太で個性豊かな焼酎」だったのです。
小宮山さんも売るのは難しいのは承知していたので、それならばしっかり売ってくれそうな酒販店を一軒一軒自らの足でまわったそうですが、その中の一軒に吉祥が入っていたのです。その時に置いていかれた名刺を頼りに弊社社長坂田が八丈島まで飛んで行きました。坂田の熱意もさることながら、吉祥の店を見ていただいたということもあり、平成20年の秋より取り扱わせていただきました。
もしあの時、小宮山さんが吉祥に来ていただいていなかったら?小宮山さんには頭が下がります。

麦冠を造る小宮山さん(左)と吉祥熊谷店長(右)。八丈島の郷土料理と堪能しました。

今では芋焼酎と言えば横浜の方でも多くの方々が楽しんでいます。
この先駆けとなり火付け役となったのが鹿児島・西酒造なんです。
鹿児島に旅した今から12年前、ある飲食店で西酒造の焼酎と出会いました。
芋焼酎らしくない柑橘系の香りのするフルーティな芋焼酎!

それが富乃宝山でした。
私はこの焼酎にすっかりはまってしまい、販売したいと思い早速蔵元へ手紙を書きます。
そして、電話。「専務は蔵に入っていて電話でれません!」と事務の方から言われました。
それから電話すること300回以上!
朝に昼に晩に電話し、結果は蔵の中か、外出・・手紙も何十通と書きました。
普通、この時点で諦めます。
実は蔵元は試していたんです。酒販店が本気かどうか?!
そうして1年半、やっと電話口に出てくれました。が、しかし芋焼酎の仕込み時期に入っており面談はできないと!それだけ神経を集中し、時間を造りに当てていました。
それから半年後の1月中旬にアポがとれ鹿児島・西酒造へ。
蔵で西陽一郎専務(現在は社長)と互いに酒に対する考えや姿勢を語り合うこと5時間。
すると突然、『坂田さんやってくれますよね!』、
もちろん『横浜でこの情熱を伝えますよ!』とがっちり握手♪
そして蔵から車で帰る際、私が車内のルームミラーから見たものは・・・。
西専務一人で腰を直角に折った礼の姿勢でした。
この時の私の体を走った衝撃は今も忘れていません。
この蔵と共に歩むと誓った時でした。
現在は蔵も当時と変わり水質のよい場所へ移転し大きくなりました。
年に何回も蔵を訪ねる私ですがいつも帰りの際は、スタッフの大勢が玄関口まで出てきていただき、あの時の西専務と同様に送ってくださいます。
信念は変わっていません。
「よい酒」は「よき人」が醸す!これが私の信条です。
横浜でも数少ない西酒造販売特約店であるKISSYO。
焼酎を「国酒」とさせるべく情熱をもって醸す西酒造。
KISSYOはこれ からも伝えてまいります。
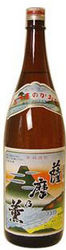
純黒、薩摩乃薫り等でおなじみ「田村合名」さんを紹介します。
鹿児島県薩摩半島の南端に位置する指宿市山川町に蔵はあります。
指宿といえば砂蒸し風呂の温泉として知られていますよね。
また薩摩富士の名で有名な開聞岳がそびえたち、景観が素晴らしい観光の町としてにぎわっています。
この休火山の開門岳から出た火山灰が降り積もってできた砂礫層からは良質なさつま芋が採れ田村合名さんは地元の農家の方と協力して芋焼酎用の黄金千貫を栽培しています。
和歌山県海南市にある平和酒造さんは、山本 保氏により昭和3年日本酒を製造する蔵として創業しました。
しかし戦争が始まり食料事情が 悪くなるにつれ酒米の確保が難しくなり、国から酒造の休業の命令が下されましたが、戦後になっても酒造再開の許可がなかなか下りず、2代目の山本 保正氏 がそれまで培ってきた経験、技術、想いを無駄にすることはなんとも忍びがたく、何度も国に掛け合い、その熱意が実って昭和25年にようやく酒造業再開の許 可が下りました。
この時、これからずっと平和な世の中が続くよう願いを込めて、平和酒造と社名を命名したそうです。

梅酒造りは平成7年より始まりました。当時はあまりにもフルーティーな梅酒のためなかなか受け入れてもらえなかったようです。と いうのも当蔵は当初から完熟梅を使用していたのですが、完熟梅は痛みが早く流通には問題があるため一般に市販されている梅酒は青梅が使用されております。
 しかし青梅はその硬さゆえに梅のエキスが抽出されにく
しかし青梅はその硬さゆえに梅のエキスが抽出されにく
く、長時間漬け込まなければなりません。
そうすると種のなかにある苦味成分まで抽出されてしまい、そ れを砂糖の甘さで抑えているのです。
梅酒を造る蔵は全国にあれど、完熟梅を使用して仕込むのは地元和歌山でなければできないことです。

そして和歌県といえばみかんをはじめ柑橘類などのフルーツの栽培がとても盛んな地域でもあります。
地元の農家さんのお力をお借りして、柚子、檸檬、夏みか んなどを使用したお酒を次々と発売されました。
ここにも「和歌山に根ざした酒造り」が活かされています。
これからも平和酒造さんの挑戦はまだまだ続くで しょう。